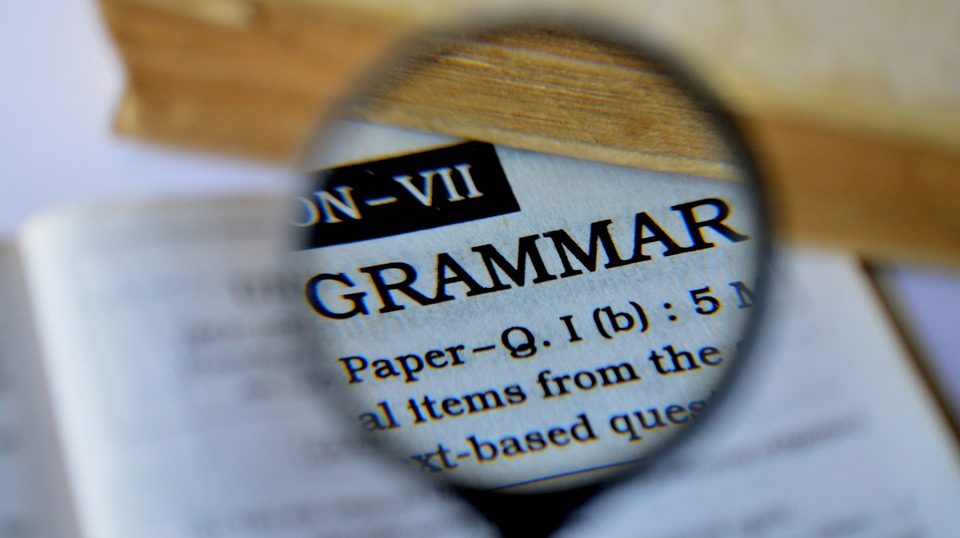モニターモデルのところで、第二言語学習には習得順序があると言いましたが、実は、この習得順序に関しても母語の影響を受けるという研究結果が出てきます。
しかし考えてみれば当たり前のことですよね。
自分の母語と似ている部分は習得されやすくなりますし、全く逆のことなどは習得しづらいということはなんとなくイメージできると思います。(母語の影響って何?ってなったかたはこちら)
っということは、韓国人には韓国人、スペイン人にはスペイン人、日本人には日本人特有の習得順序があるということになります。
クラッシェンのモニターモデルでは、一つの習得順序が示されていましたが、母語によってその習得順序は変化します。
1974年にデュレイとバートという研究者は文法習得の順序を示しました。
左側が一般的に言われている習得順序です。
しかし、その後の研究でこの文法の習得順序にも母語の影響が関わっているということがわかりました。
右側が日本人の英語習得順序です。(ここでいう「習得」とは、無意識にでも使える状態になることを指します。)

(鈴木孝明・白畑知彦、ことばの習得 母語習得と第二言語習得、2012)
比べてみると分かりますが、日本人は所有格のsの習得が一般的な習得順序に比べて早めにきています。
日本語の「の」の使い方と似ているため、日本人にとっては所有格のsは習得しやすいんですね。
一方で冠詞に関しては、日本人の習得順序の方が遅くなっています。
おそらく僕たち自身にも自覚はあると思いますが、冠詞のaやtheの使い分けは非常に難しく感じられます。
これは日本語に冠詞の概念がないため習得が困難だと言えます。
では、この習得順序を知ることになんのメリットがあるか。
それは、「間違えた時に納得できる」ということと、「習得順序通りに学習することで効率的に学習することができる」ということです。
つまり、僕たちは、英語を話す時に、
「うわ、三単現のsまた忘れた」
というようなことによく気づくと思います。
ルール自体は非常に簡単な文法項目なので、みんな間違いに気づくんですね。
そして、
「こんな簡単な文法も使えんとか全然ダメや・・・」
って感じる人が多くいます。
しかし、その時に習得順序について知っていれば、
「ルールは簡単な文法項目でも、習得するにはかなり難しい項目なんだ」
と納得でき、落ち込む心配がなくなります。(これは情意フィルターにも影響しますよね。)
また、この習得順序から、学習初期の段階でいきなりaとtheの違いを理解しようとすることは、非常に効率の悪い学習だとわかります。
内容的にも難しい上、使いこなすことは、ほぼ不可能です。
逆に連結辞のbe(後ろに分詞以外の形容詞、名詞が来るパターン*)などは習得しやすいため、学習の初めはbe動詞から学習することが効率的だということもわかります。
*ex)I am a student.
He is happy.
もちろん、習得順序に従った学習のみで英語力を上げていくことは不可能と言えますが、この習得順序を意識して、自分の学習の中に取り入れることにより、学習効率は確実にあげることができます。
なので、文法学習のさいには上の表に出ている習得順序を意識してみてください!